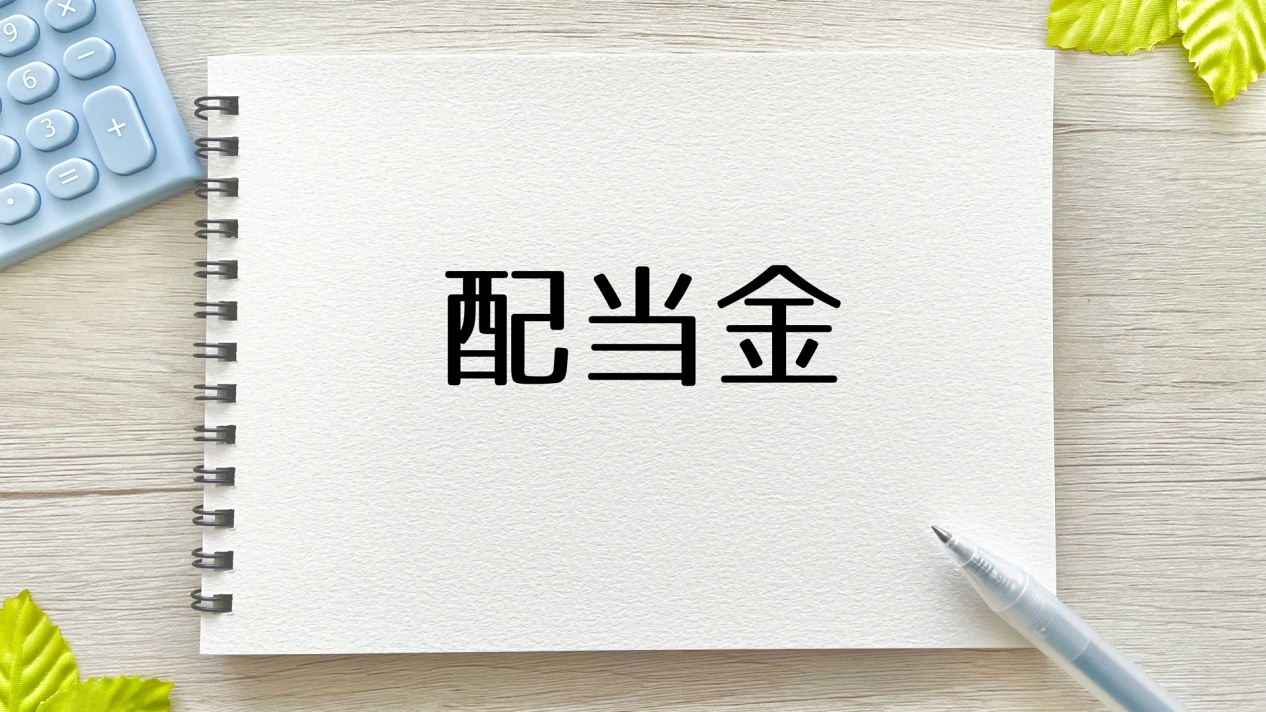悩んでいる人
悩んでいる人VYMで毎月1万円・3万円・5万円の配当金を得るにはいくら必要?
このような悩みに答えます。
- VYMで毎月1万・3万・5万の配当金を得るには?
- VYMで配当金生活を達成するのは難しい
- 投資信託・ETFの買い方
- VYMの配当金に関する注意点
VYMは米国高配当株ETFのうちの1つであり、多くの高配当株が含まれています。
このVYMから定期的に支払われる配当金を活用し、配当金生活を目指す人もいるでしょう。
結論から言うと、月1万円の配当金を得るには400〜500万円、月3万円の場合は1,300〜1500万円、月5万円の場合は2,200〜2,800万円ほど必要です。
本記事では、VYMで毎月1万円・3万円・5万円の配当金を得るにはいくら必要かについて詳しく解説します。
なお、VYMに投資するには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
| おすすめのネット証券 |
|---|
| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |
VYMで毎月1万・3万・5万の配当金を得るには?
毎月1万・3万・5万得るのに必要な額
毎月1万・3万・5万得るのに必要な額は以下のとおりです。
シミュレーションの条件
- 1ドル=100円
- VYMの配当利回りは3%程度であるため3%
- 課税口座では国内分(20.315%)のみ、NISA口座(非課税口座)では米国分(10%)のみ課税
| 配当金 | 必要額 | |
| 課税口座 | 月1万円 | 502万円 |
| 月3万円 | 1,506万円 | |
| 月5万円 | 2,800万円 | |
| NISA口座(非課税口座) | 月1万円 | 444万円 |
| 月3万円 | 1,333万円 | |
| 月5万円 | 2,222万円 |
月1万円の配当金を得るには400〜500万円、月3万円の場合は1,300〜1500万円、月5万円の場合は2,200〜2,800万円ほど必要です。
また、VYMはドル建ての商品であり、円安が進むとより多くの円を投資しないと同じ額の配当を得られなくなります。
現在は1ドル140〜150円の円安が続いているため、実際に配当を得るには上記の1.4〜1.5倍ほどの投資額が必要になるでしょう。



高配当と言えど、実際に毎月数万円の配当金を得るには、相当な投資額が求められることが分かります。
VYMに積立投資する場合はいくら必要?
実際にVYMに投資する際はまとまった額を一括投資するよりも少額から積立投資すると思います。
以下の表は年3%複利運用しながら毎月積立したときに、何円ずつ積立すれば目標となる配当を達成できるかを示したものです。
【NISA口座の場合】
| 積立期間 | 月1万円配当 | 月3万円配当 | 月5万円配当 |
| 10年 | 34,800円 | 104,400円 | 174,000円 |
| 15年 | 22,100円 | 66,300円 | 110,500円 |
| 20年 | 15,300円 | 45,900円 | 76,500円 |
| 25年 | 11,400円 | 34,200円 | 57,000円 |
| 30年 | 9,000円 | 27,000円 | 45,000円 |
配当金(分配金)は課税対象
外国資産(株式・不動産)や外国資産に投資を行う投資信託から得られた分配金に対して、投資先の国ごとに所得税に相当する税金(以下「外国所得税」)がかかる場合があります。
NISA口座(非課税口座)を利用しても国内での課税(20.315%)は非課税にできますが、外国所得税は免除されません。



例えば、米国企業に投資する投資信託の分配金には、米国で10%の税金がかかります。
なお、分配金は外国所得税が源泉徴収された後に入金される仕組みであるため、個人が特別な手続きを取る必要はありません。
加えて、オルカンなどの基本的に分配金を支払わない投資信託は、源泉徴収された後に自動で分配金が再投資されます。
課税口座(一般口座、特定口座)を利用している場合はどうなる?
課税口座を利用している場合、分配金に対して二重に課税されます。
例えば、米国企業に投資する投資信託の分配金には、米国で税金(10%)が源泉徴収された後に国内分(20.315%)が課税されます。
なお、二重課税となっている場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することで外国税の一部または全部を取り戻すことが可能です。
外国税額控除の詳細については「No.1240 居住者に係る外国税額控除」をご覧ください。
VYMで配当金生活を達成するのは難しい
月5万円の配当金を得るのに2,200~2,800万円ほど必要なので、VYMで配当金生活を達成するのは難しいです。
しかし、VYMなどの高配当株ETFには、定期的に配当金という形で実際に使えるお金を受け取れるというメリットがあります。
インデックス投資は市場全体の成長に長期的に投資する手法ですが、投資信託を売却しない限り利益は発生しません。
「頭と尻尾はくれてやれ」という投資の格言があるように、売却の判断は購入よりも難しく、特に暴落時には心理的なハードルが高くなる傾向があります。
その点、高配当株ETFは、売却を考えなくても定期的に配当金という形で収益を得られるため、精神的な負担が軽減されます。
VYMに投資する際は、多額の配当金を期待しすぎず、「少しずつ資産を増やしながら、定期的に収入が得られる手段の1つ」として捉えるのが適切です。
資産形成のメインとしてではなく、補助的な収入源として活用することで、投資の幅を広げることができるでしょう。
投資信託・ETFの買い方
投資信託・ETFの買い方は以下のとおり。
- 証券口座を開設する
- 投資信託・ETFを購入する
①証券口座を開設する
投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
【SBI証券】
- ネット証券最大の1,300万口座突破
- 国内株式個人取引シェアNo.1
- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能
【楽天証券】
- ネット証券最大の1,300万口座突破
- 国内株式個人取引シェアNo.1
- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能
【マネックス証券】
- 高還元率のクレカ積立が魅力
- dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能
【三菱UFJ eスマート証券】
- auユーザーにおすすめ
- Pontaポイントが貯まる・使える
- 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能



クレジットカードで積立するとポイントが還元されます。
②投資信託・ETFを購入する
投資信託の購入方法
証券口座を開設したら投資信託を積立購入します。
つみたて投資枠、成長投資枠とは?
新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。
つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。
そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。
なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。
ETFの購入方法
証券口座を開設したらETFを購入します。
ETFの注文方法は個別銘柄と同じですが、海外ETFに関しては「外国株式取引口座」の開設が必要な証券会社もあるので、国内ETFと海外ETFに分けて紹介します。



外国株式取引口座とは、外国株式や外国投資信託等を売買する際に開設が必要な口座のことです。
【国内ETF】
- SBI証券:「Webページにアクセス」→「国内株式」→「ETF・ETN」
- 楽天証券:「Webページにアクセス」→「国内株式」
- マネックス証券:「Webページにアクセス」→「商品・サービス」→「株式取引」
- 三菱UFJ eスマート証券:「Webページにアクセス」→「お取引」→「現物株式」
【海外ETF】
- SBI証券:
- 外国株式取引口座の開設が必要→外国株式取引口座開設方法
- 「Webページにアクセス」→「外国株式・海外ETF」→「海外ETF」
- 楽天証券:
- 外国株式取引口座の開設は不要
- 「Webページにアクセス」→「外国株式」→「海外ETF」
- マネックス証券:
- 外国株式取引口座の開設が必要→外国株式取引口座開設方法
- 「Webページにアクセス」→「商品・サービス」→「外国株」
- 三菱UFJ eスマート証券:
- 外国株式取引口座の開設が必要→外国株式取引口座開設方法
- 「Webページにアクセス」→「お取引」→「外国株式」
なお、米国ETFなどの海外ETFの購入方法として、「円貨決済」と「外貨決済」の2種類があり、外貨決済の方が低コストなので、外貨決済を選ぶと良いでしょう。
VYMの配当金に関する注意点


VYMの配当利回りは変動する
VYMは高配当株ETFとして知られていますが、その配当利回りは固定されているわけではありません。
| 2014年 | 3.06% |
| 2015年 | 3.13% |
| 2016年 | 3.30% |
| 2017年 | 3.17% |
| 2018年 | 3.09% |
| 2019年 | 3.64% |
| 2020年 | 3.11% |
| 2021年 | 3.38% |
| 2022年 | 2.90% |
| 2023年 | 3.21% |
| 平均 | 3.20% |
市場環境や経済状況の変化に応じて変動し、企業の収益が向上すれば増配される可能性がある一方、業績が低迷すれば減配のリスクもあります。
また、VYMは時価総額加重平均型のETFであり、構成銘柄の入れ替えや配当方針の変化によっても、配当額や利回りに影響が出る可能性があります。
過去の配当実績を参考にすることはできますが、それが将来の配当額を保証するものではない点には注意が必要です。



ただ、VYMの配当利回りは安定しているので、あまり心配する必要はありません。
VYMの配当利回りは高くない
米国高配当株ETFにはVYMの他にもHDVやSPYDがあり、VYMの配当利回りは他と比較して特別に高いわけではありません。
| HDV | 3.72% |
| SCHD | 3.72% |
| SPYD | 4.84% |
| VIG | 1.73% |
| VYM | 2.90% |
ですが、VYMの銘柄数は約500であり、業種のバランスも良いため、安心して長期保有したい方にとって最適な選択肢となるでしょう。
配当金は米ドルで支払われる
VYMの配当金は米ドルで支払われるため、実際に受け取る金額は為替レートの影響を受けます。
円安の状況では1ドルあたりの円の価値が低くなるため、受取額が増加しますが、円高になると受取額は減少します。
このように、為替レートはVYMの配当金を受け取る際に重要な要素となり、投資家は為替リスクも考慮する必要ことが必要です。
まとめ
今回はVYMで毎月1万円・3万円・5万円の配当金を得るにはいくら必要かについて解説しました。
- VYMで毎月1万・3万・5万の配当金を得るには?
- VYMで配当金生活を達成するのは難しい
- 投資信託・ETFの買い方
- VYMの配当金に関する注意点
月1万円の配当金を得るには400〜500万円、月3万円の場合は1,300〜1500万円、月5万円の場合は2,200〜2,800万円ほど必要です。
また、VYMはドル建ての商品であり、円安が進むとより多くの円を投資しないと同じ額の配当を得られなくなります。
現在は1ドル140〜150円の円安が続いているため、実際に配当を得るには上記の1.4〜1.5倍ほどの投資額が必要になるでしょう。
高配当と言えど、実際に毎月数万円の配当金を得るには相当な投資額が求められ、VYMで配当金生活を達成するのは難しいです。
しかし、VYMなどの高配当株ETFには、定期的に配当金という形で実際に使えるお金を受け取れるというメリットがあります。
VYMに投資する際は、多額の配当金を期待しすぎず、「少しずつ資産を増やしながら、定期的に収入が得られる手段の1つ」として捉えるのが適切です。
資産形成のメインとしてではなく、補助的な収入源として活用することで、投資の幅を広げることができるでしょう。
なお、VYMに投資するには証券口座を開設する必要があります。
まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。
| おすすめのネット証券 |
|---|
| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |
| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |